電気設計のプロとして仕事ができる環境――安全を当たり前にするために
技術営業部 Y.H × 技術営業部 Y.M
三笠精機の強みは、制御盤の設計から製造まで自社で手掛けられることです。特に近年は、海外規格対応の分野で力を発揮しています。北米や欧州に輸出する装置内の制御盤を、設置される国・地域のルールに則ったかたちに適合させるーー専門的でニッチな仕事ですが、その業務内容や仕事への想いについて、設計部門で働く二人の社員に話を聞きました。
「大手でも苦労する」海外規格対応の難しさとは?
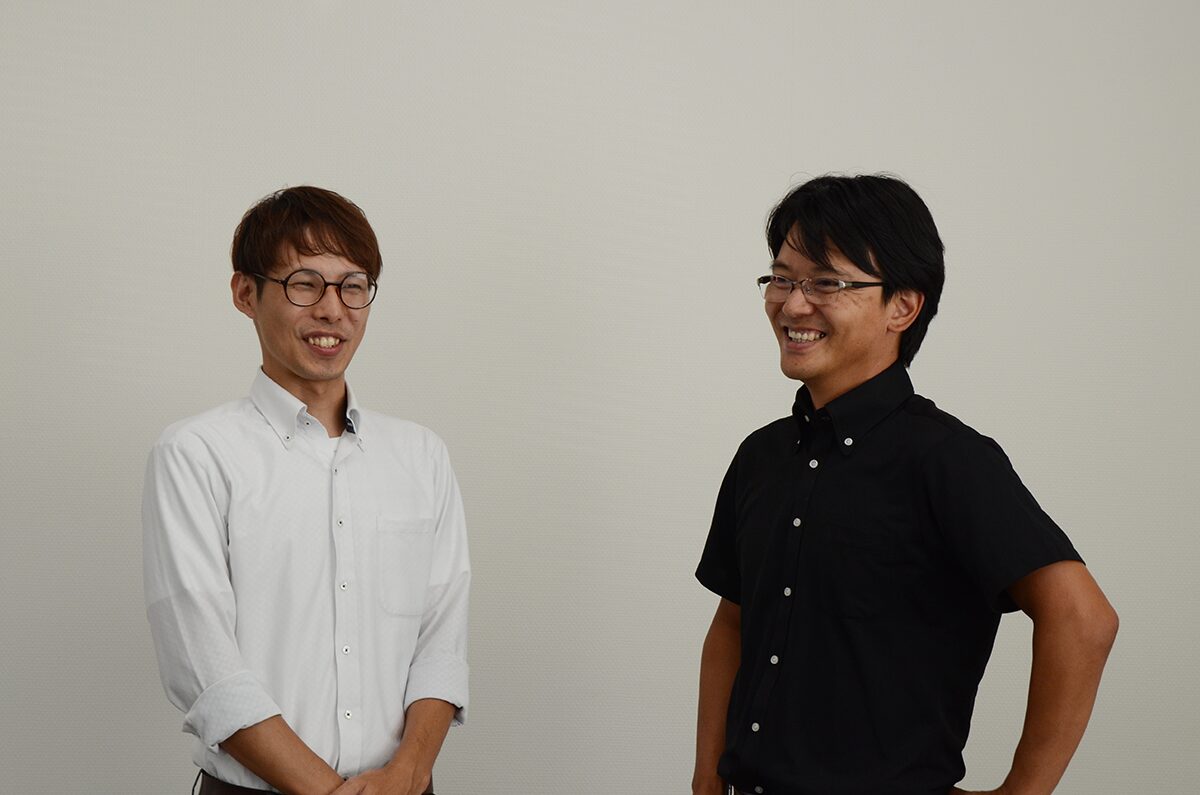
――Hさんは2008年、Mさんは2018年入社で、同じ設計部門の先輩後輩です。お二人にとって印象に残る案件があれば教えてください。
Y.H(以下H):今は各々別の案件を担当していますが、数年前に手がけた、大手メーカーの装置輸出案件が印象に残っています。
Y.M(以下M):まずは私がコンサルティングに入り、その後Hさんがリスクアセスメントを行ってくださった案件ですね。初めて装置を輸出するとのことで、お客さまは「何から手を付けて良いのかもわからない…」とお困りでした。先方に予期せぬ、避けられないトラブルが起きて、スケジュールがぎりぎりになったことを覚えています。ただその後もお取引が継続するなど、信頼関係が構築できたのは嬉しかったですね。

――「何から手を付けて良いかわからない」という依頼は多いのでしょうか?
H:規格書は当然ながら日本語ではありません。ですから、専門用語が並ぶ膨大な外国語の文書を読み解くことが最初のハードルです。さらに規格を解釈し装置に実装させるための参考情報が少ないこと、情報にアクセスしにくいことも、規格対応を難しくする原因となっています。
専門コンサルタントに相談するのも手ですが、彼らは製造に関する知見を持っていない。納品までの期間やコストを圧縮するために、優先度に応じた対応をどう行うかなど実務に即した分野まで対応できるのは、うちの強みだと思います。
安全を重視するよう、上流工程にモノ申す
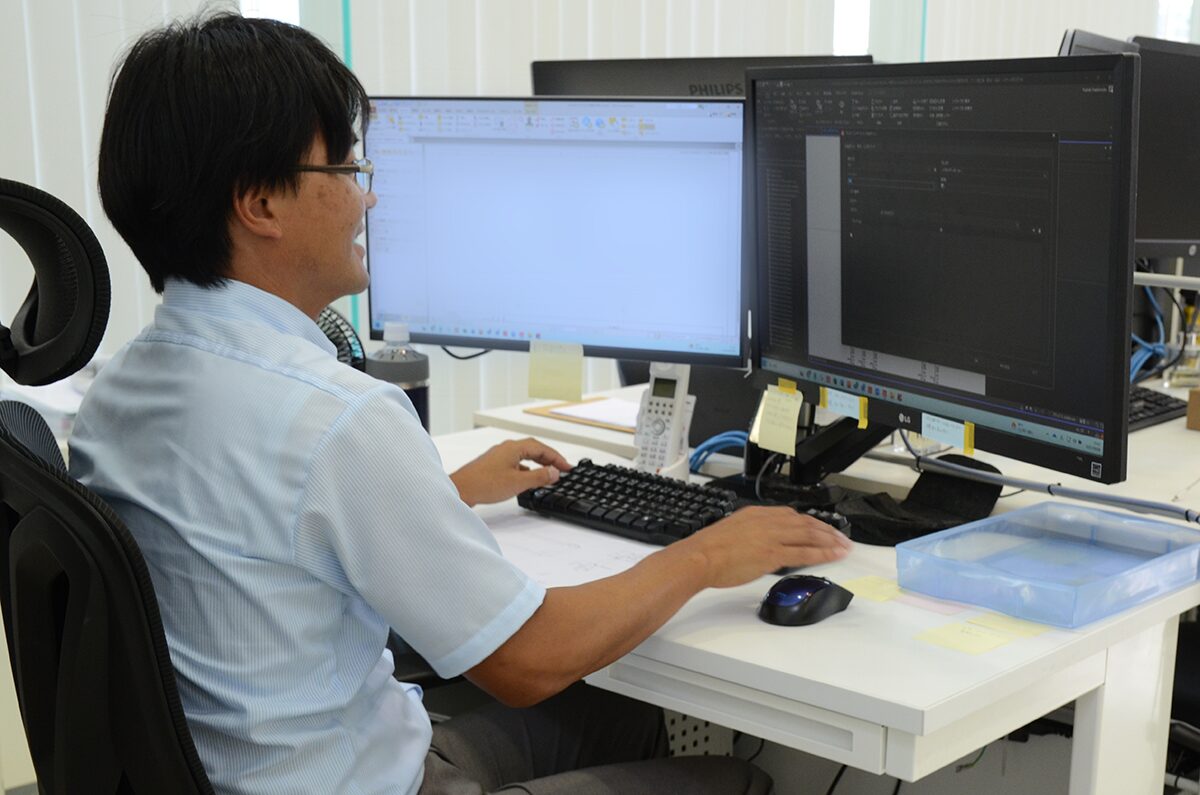
――その強みを活かし、お客さまの課題にお応えできるのが三笠精機での仕事の醍醐味と言えそうです。
M:それも一つの魅力ではありますが、「電気設計技術者として専門性を活かせること」が大きいと思います。
装置の設計・製造の現場で電気設計の工程は最後尾。安全性を担保する重要な立場であるのにも関わらず、現場では軽視されがちです。時として「とにかく動けばいいじゃん!」などと言われることすらあります。
H:装置安全の立場からみると問題点が目立つということは、往々にしてあります。しかし三笠の仕事は、「その設計、危ないですよ」と伝え、要望を設計に反映すること。機械安全に関する知識と技能の保有を認証する資格である『セーフティアセッサ』を取得しており、装置安全のスペシャリストとしての立場からも専門性を活かして正しいことを主張でき、安全性を担保できる。電気設計の技術者にとって、このような環境はあまりなくやりがいを感じられると思います。
「自律的に仕事をハンドリングしたい人は向いている」

――お客さまへの説明や提案というシーンを考えると、規格への理解、幅広い知識なども必要そうです。
H:規格への理解、説明方法については、基本のロジックを押さえたうえで、経験を積み重ねていけば大丈夫でしょう。
あとは、志向性としては自分で動けること、つまり自律的であることが重要になってきますね。また、ゼロイチがやりたい人、仕事を自分でハンドリングしたい人などが三笠に向いていると思います。
M:確かに三笠の設計分野は装置の一部である制御盤に特化してはいるものの、最初から最後まで全部ひとりで手がけることが多いんです。
例えば装置メーカーに在籍していて、ひたすら装置の一部分を過去の図面をもとに改良を続ける仕事が合わないといった思いを抱えている方には、当社の環境はおススメです。

――そういえば、設計やコンサルティングに加え、ウェビナー講師も担当していますよね。
H:私は海外規格案件を増やすなか、集客策としてセミナーをやることになり、講師役に指名されたのがきっかけです。当時は「こんなに知識がないのに、セミナーをやるの?」と、あまり積極的ではなかった記憶があります。
M:Hさんが積極的でないこともあるんですね…。この機会に聞いちゃいますが、Hさんて、仕事ができなくて落ち込んだりすることってありますか?
自分の能力を超えそうなことがあると、まずやろうとしますが、まぁ壁にぶち当たるじゃないですか。で、ぶち当たるたびにだんだん心が削れてく感覚というか…。
H:うーん正直に言うとよくわからない 笑。できなければ「ごめんなさい」するしかないので。
M:私はいつも、仕事はお金をもらっているので、ある程度そこに費用対効果というか「金額相応の満足感を出さなきゃいけない」というプレッシャーがありますね。

――とはいえ、お二人とも、とても楽しそうに仕事をしているように見えます。
M:へこんでいてもしょうがないからですかね。…と言いつつも、毎回へこみますよ。ただ自分の仕事は最後まで自分がやるしかないですから。
Hさんに頼りきりにならず、なるべく負担を減らしていこうという思いはいつもありますね。
――Hさんからみて、Mさんの仕事ぶりは?
H:自分でやれるようになっていますし、もう十分じゃないかな?と思います。なんですかね…特に不安がないというか…。
M:またそれがプレッシャーになりそう(笑)。いや「もうどうでもいいや」と思っていたら、別に気にしないんですが、やっぱり裏切りたくはないんです。
それはお客様に対しても同じで、頼ってもらうと嬉しいですし、助けになりたいとの思いはあります。
H:それで言うと、私の仕事の喜びは、「うまくいく」ことですかね。例えば特急案件が無事間に合ったときの「よっしゃ!」という感覚。達成感というか、目の前の課題についてパズルを組み合わせて解決する喜びが、この仕事の楽しさですね。
安全を当たり前にするために
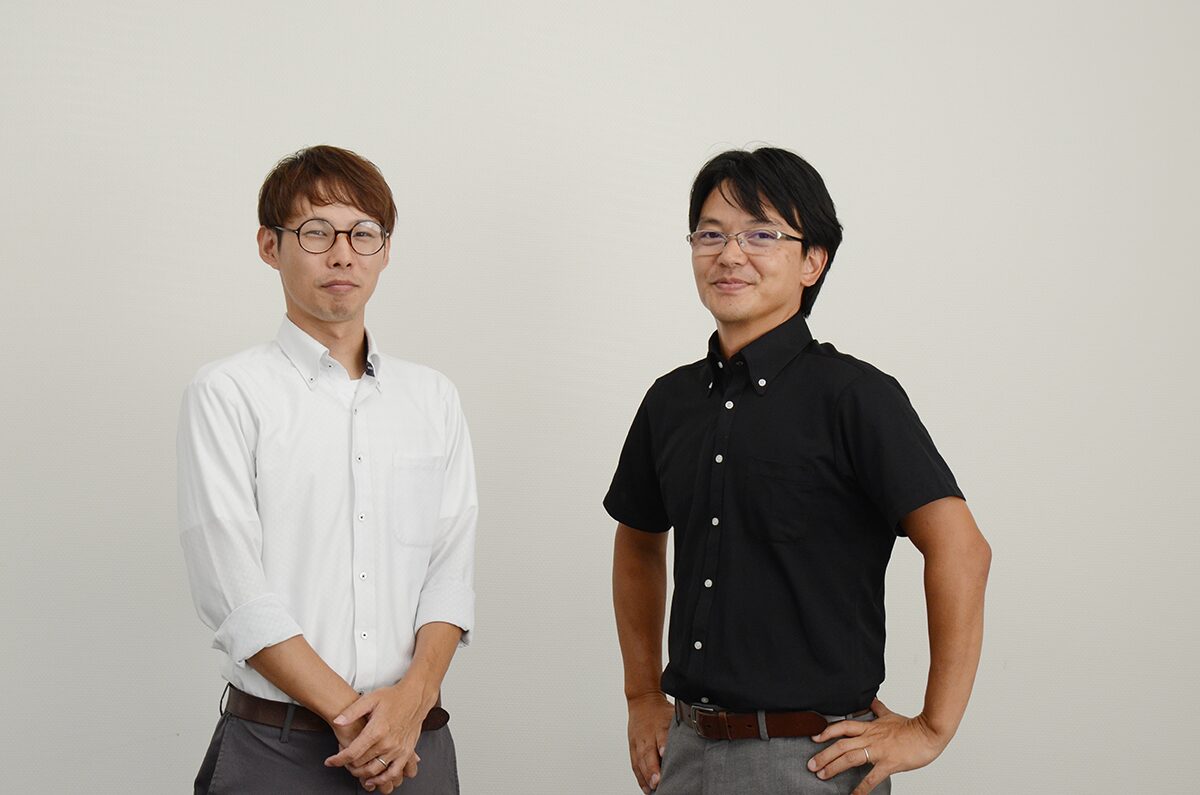
――最後に、お二人の将来の目標や仕事の在り方などをお聞かせください。
M:今後間違いなく需要は増えていくと思っています。一方で、例えば大きな組織だったら専門的な部署ができるなど、対応できる人も増えていくのではないでしょうか。つまり、私たちの希少性みたいなものは薄れていくわけで、何か別の武器を持たないとなぁとは思っています。
H:私たちが手掛ける分野は、安全のためにやるべき「普通」のことです。現在、海外規格対応の需要は多く、コンサルティングの単価もそこそこの価格ではありますが、その「普通」をより簡単に、誰でもできるようにするとか、そういうことを考えられるといいなと思っています。
